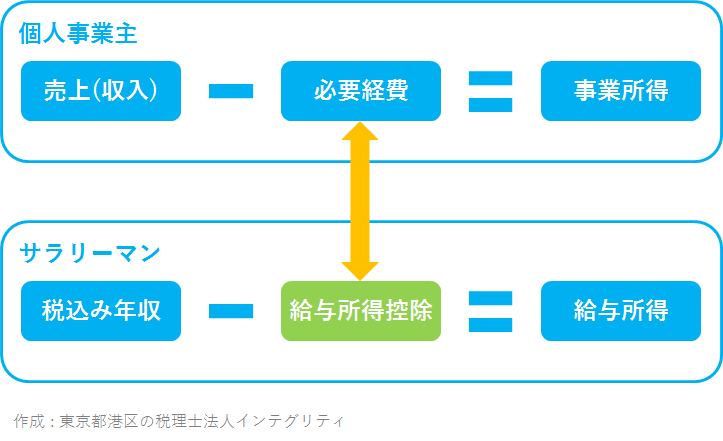はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。
今回は、身近な税金である印紙税と収入印紙の基礎として、印紙税の税務調査について説明したいと思います。
印紙税と収入印紙については下記のページも参照ください。
印紙税・収入印紙の基礎 | 印紙税の概要
印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の概要
印紙税・収入印紙の基礎 | 領収書に貼る収入印紙の金額
印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の仕訳・経理
印紙税の税務調査はいつ行われるのか
株式会社などの法人の税務調査では、法人税とともに源泉所得税や消費税などが調査されます。
フリーランス・個人事業主の税務調査では、所得税とともに源泉所得税や消費税などが調査されます。
そして、法人、個人ともに税務調査においては印紙税についても同時に調査されます。印紙税だけを調べるために税務調査が入るということは基本的にはありません。
印紙税の税務調査の内容
印紙税の税務調査では何が調べられるのかという具体例を紹介します。
収入印紙の購入枚数と領収書の控えの枚数を見比べて大きな差がないかチェックする。
例えば、
収入印紙の購入枚数が年間100枚、
5万円以上(平成26年4月1日以前は3万円以上)の領収書の控えの枚数が150枚であったとすると、
50枚の差があることになります。この50枚の差が出た理由を問われます。
収入印紙が必要な契約書で、収入印紙が貼られていないものはないかをチェックする。
貼られてある収入印紙が、印鑑やサインでちゃんと消印されているかをチェックする。
領収書や契約書以外の書類についても、収入印紙を貼る必要がある課税文書に該当する書類がないかどうかチェクする。
税務調査で印紙税の誤りが発見されたら
税務調査で印紙税の誤りが発見されたら、過怠税という税金ペナルティを納めなければなりません。
印紙税の過怠税
課税文書(領収書など印紙税を貼って消印する必要がある文書)の作成者が、
課税文書を作成して相手に渡す時までに、
収入印紙を課税文書に貼っていなかった場合は、
本来貼るべきであった収入印紙の金額に加えてその2倍の金額(合計で本来貼るべきであった収入印紙の金額の3倍の金額)を過怠税として納めなければなりません。
過怠税は、税金のペナルティであるため税金計算上の経費(会社の損金や個人事業主の必要経費)にすることができません。
本来貼るべきであった収入印紙の3倍の金額の全てが過怠税になります。本来貼るべきであった収入印紙が合計で1万円であった場合は、その3倍の3万円が過怠税になります。
本来貼るべきであった収入印紙の金額は経費になって、その金額の2倍分だけが過怠税として経費にならないわけではないので注意してください。本来貼るべきであった収入印紙の合計1万円は経費になって、その金額の2倍分である2万円が過怠税として経費にならないのではありません。
なお、課税文書に収入印紙は貼っていたけれども消印をするのを忘れていた場合は、本来貼るべきであった収入印紙の金額と同額を過怠税として納めることになります。収入印紙を貼らなかった場合の3倍に比べると緩くなっています。消印を忘れた収入印紙の金額は会社の損金や個人事業主の必要経費になりますが、過怠税は損金や必要経費にはなりません。
消印を忘れた収入印紙の金額の合計が1万円であった場合は、その1倍の1万円が過怠税になります。消印を忘れた収入印紙の1万円は経費になりますが、過怠税の1万円は経費になりません。
税務調査の前に収入印紙の貼り忘れに気づいたら
税務調査の前(正確には税務調査が入るという連絡が来る前)に収入印紙の貼り忘れに気づいた場合、「印紙税不納付事実申出書」という書類を税務署に提出すれば、過怠税として3倍納付しなければならないところを、1.1倍の過怠税で済みます。
おわりに
港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。